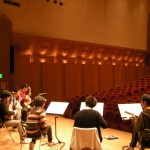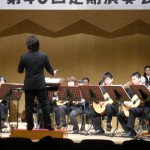2010.04.20
4月も半ばになりましたが、あまり暖かくなりませんね。先日は大荒れで雪も降りましたが・・・
とはいえ、入学式も9日に終わりまして学内の各サークルが新入部員獲得のためにしのぎを削るであろう新歓の季節になったわけですね。
はっきり言ってあまり手ごたえがよくないような気が…入学式も食いつき悪かったし見学の出足もよくないような。まあ、まだ前半戦ですので勝負はこれからといったところです。
音楽系サークルの隙間(派手でもなく有名でもない)であるマンドリンサークルに新入生が来るのか。はたして新歓コンパはどうなるのか。以前友人に「マンドリンってなんか黒魔術っぽい名前だね」(実話)といわれるサークルに未来はあるのか。
新入生が入り次第、続報を流そうかなと思います。
ここからは余談です。
勝毎に載ってましたが、コミュニケーションプラザ(仮称:旧学生会館)が完成し私たちも利用を始めました。ほんとに学館をベースに作ったとは思えないほどきれいです。その分利用の制約が多くなりましたが…

中はこんな感じ。明るくて清潔感あふれる内装(なんか宣伝みたい・・・)
とはいえ、うちのサークルはちょっと(というか大分)優遇してもらい、物品庫を長期貸し出ししてもらっています。以前の共用室より少し広い位の部屋でサークルの物(楽器やら雑品やら)が全部入りました。これから整理しますがこんな感じです。

楽器がたくさん・・・

雑品も山のように・・・減らしましたが

これからは大抵一階のこんな部屋で練習してます。う?むきれい。
2009.12.14
当日の様子を撮った画像となりますのでリハーサルの様子も含めました。
枚数も多く、選ぶのに一苦労でしたね。
三年生の皆様お疲れ様でした、これからは大学の研究やゼミなどで忙しくなると思いますが、
寒くなって、根雪にもなり始めましたので大病、怪我などお身体の方大事にしてください。
2009.12.01
今日から12月、もう氷点下になる日も珍しくなくなってきました。
さて、本日からマンドリンサークル練習再開です。
2年生と1年生で目下のところは卒演を目標にやっていきます。
ちなみに新幹部もおおよそ決まりました。そのうち挨拶をあげます。
一年間、よりよい演奏を目指して楽しくがんばっていきましょう。
?
追伸・コメントありがとうございます!
今まではコメントのとこに返信つけていたのですが、なんか違う気がしたのでこっちにのっけます。
丸本さんの曲はやっぱり耳に残りますね。私はたまに森の鼓動が流れてきます。
連載のほうは…まあノープランなんですがCDを端から行こうかなと思ってます。
これからは聞かないと記事がかけなくて正直面倒・・・いや、勉強になりますのでいいペースでやりたいと思います。
?
追追伸・週末に札幌マンドリンアンサンブルの定期演奏会を聞きに行きました。
内容としては
一部?映画音楽特集 二部?スペイン特集 三部?青春音楽特集
でした(曲目はパンフレットが手元にないので失礼)。わからない曲もありましたが聞きなれた曲も多く、最後まで飽きないうまい構成になっているなと感じました。
マンドリンオーケストラに管楽器や打楽器、今年はピアノを加えての演奏会でしたが、やっぱりノリのいい曲はドラムが利いててよかったです。奏者さんは三部が一番大変そうだと感じましたが、一番楽しいステージでした。マンドリンでまさかロック音楽(ローリングストーンズの)を入れてくるとは・・・すごいです。
スペイン特集は確か「スペイン」「狂詩曲スペイン」の二曲でしたが、曲(あるいは音)の作り方の巧妙さが一部と同様に出ていたと思います。「歌う」とか「強弱をつける」とはよく言うものですが、音量の波のつけ方、つまり小さい音から大きい音までの出し方が本当にすごい。さっきからすごいしか言ってませんが、勉強になりました。
個人的には映画音楽、やりたいなと思う今日この頃です。
最後に斉藤先生。いい声でした!
2009.11.27
もう、定演終わってるじゃあないか!でも書きます(というか引用です。申し訳ない)。
?
虹彩は2006年、京都教育大学マンドリンクラブ第47回定期演奏会において初演された。
曲は展開部的な性質の中間部を有する三部形式によるが、2つのモチーフと1つのテーマ、および作者の前作である「雨の世界」と「光彩」の引用によるエピソードという多彩な音楽要素が絡み合い、様々な響きを示している。上昇形の「雨の世界」のモチーフはおそらく雨が上がる描写であり、その後に光が差し、虹が現れるという様子が描かれる。また、2度の進行による響きの変化が全曲を支配しており、それが光をプリズムに通したように、様々な色を聴くものに見せる。
?― 作曲者記 ―
自然に見える景色の中で、虹は
その鮮やかな色彩、
一瞬にして現われ消えてしまう儚さ、
空いっぱいに広がる壮大さ、
一方で小さく、触れることが出来そうなくらい身近にも見ることの出来る
とても不思議な存在だと思います。
この曲は私が虹に感じる色彩や想起される感情を曲想としています。
本来は、人間の瞳の色を決定し、目に入る光の量を調節する部分の事を「虹彩」と呼びます。
この曲名には虹を見た一人の人間の心象であるという意味を込めました。
とのことでした。奥の深い曲です。
?
今後の連載ですがたまにはやろうと思います。
サークルに保管されている楽曲データは結構あるので聞いた感想とかを書き込んでいきたいです。
音楽の道も日々是精進ですね。
2009.11.13
最近、サボり気味でしたがとりあえず三部の楽曲については定演までにすべて上げたいものです。
それでは、丸本大悟氏について今回は見てみましょう。
(以下HPを参考にしています)
丸本大悟氏は1979年大阪に生まれ、5歳よりエレクトーンと楽典の基礎を学びはじめました。
マンドリンを始めたのは大学在学中であり、龍谷大学マンドリンオーケストラマンドラ首席奏者となりました。その後ARSNOVA Mandolin Orchestraでマンドラ奏者となり、
現在はARTE MANDOLINISTICA 及び ARSNOVA Mandolin Ensemble にて同じくマンドラ奏者として演奏を行っています。
作曲活動は高校よりはじめ、ARSNOVA解散公演の為の「ARSNOVA組曲」「組曲『杜の鼓動』」をはじめ、数多くの作曲委嘱を手がけ、作品にはマンドリンオーケストラ曲の他、アンサンブル曲、独奏曲、編曲作品などがある。
2006年、第2回大阪国際マンドリンコンクール作曲部門にて独奏曲「Four Preludes」が入選、アンサンブル曲「光彩」が第3位入賞。
マンドリン、マンドラを井上泰信氏に師事し和声法を久保田孝氏に師事しました。
?
昨年はうちのサークルでも上記にある「組曲『杜の鼓動』」の第三楽章「街の灯」をやりましたが、月並みな感想ですが「すごくいい曲」でした。難しい曲なのですが・・・。第一楽章から第三楽章まで聞けばわかりますが、非常に情景が浮かぶ、ただ聞くだけでもたのしい曲です。非常にメロウなフレーズから緊張や激しさに満ち満ちた部分まであり、やはり第三楽章は組曲の最後にふさわしい曲です。
弾く方とすると、常によい緊張感を持ちながら弾ける曲です(私はそれどころではなかったですがね)。というのも、似たようなフレーズが使われているため、そこの表現をどうするかに気をつける必要が常にあるからなんですが、曲の持つ緊張感がそのまま来るという感じかも知れません。
さて次回は「虹彩」についてです。たぶんあっさりとしかかけないと思いますが・・・